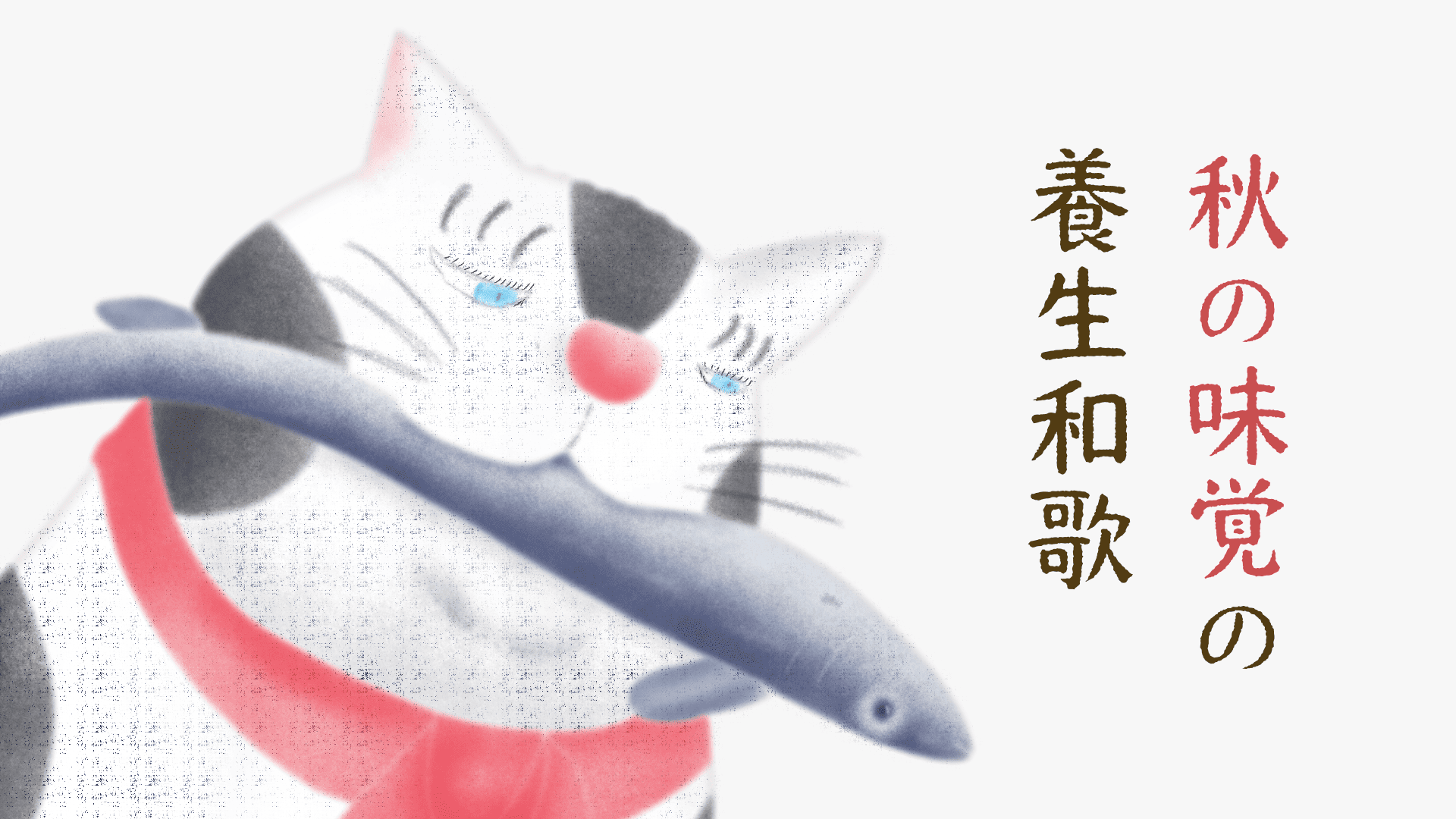
江戸時代の養生和歌
江戸時代には養生法や食べ物の効能を、和歌形式で紹介している本が多数あります。今回は江戸後期の『食品国歌』に収められる和歌から、秋の味覚についての歌を集めてみました。秋が旬の物を食べて、夏の疲れを癒し、冬に備えるようにしましょう。
栗(くり)
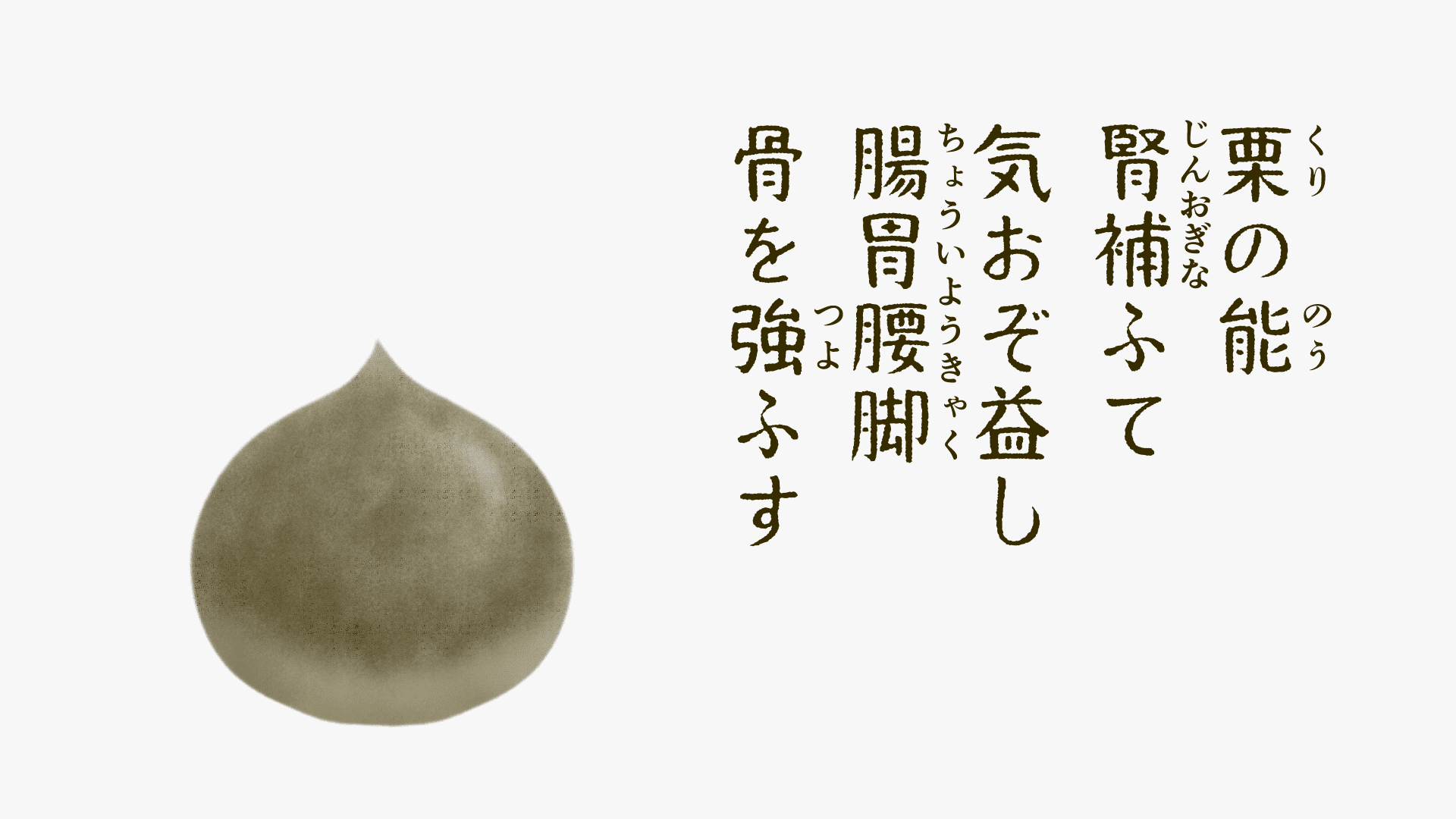
クリは補腎と益気の効果があり、夏の疲れが出る秋にはもってこいの食材。そのままでも食べやすく、栗ご飯などにしても美味しい。
薩摩藷(さつまいも)
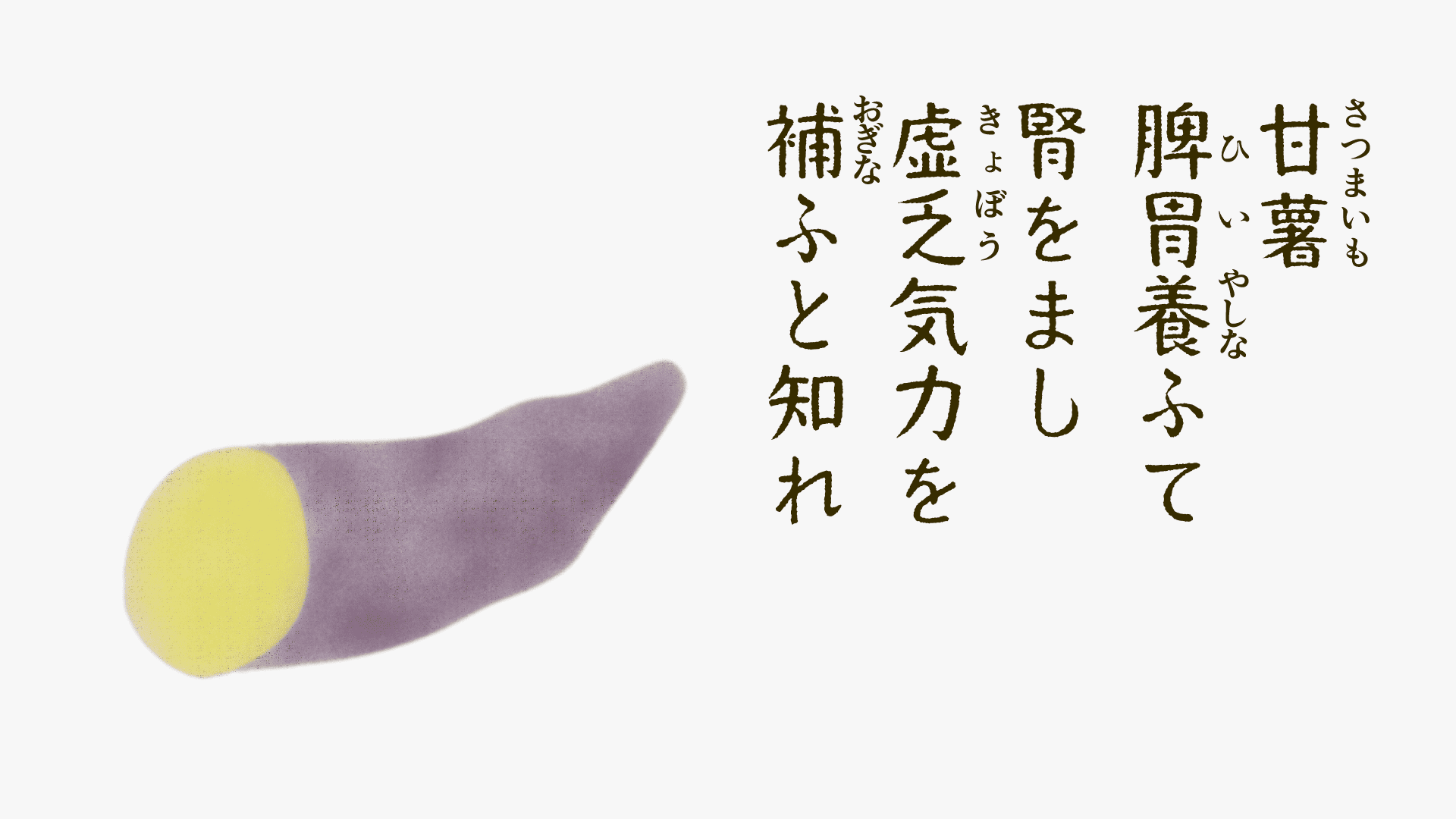
サツマイモは補腎に加えて脾胃を養う効果がある。『本草綱目』には「功は薯蕷に同じ」とあり、漢方の補剤で用いられるヤマイモ(薯蕷)と同等の効果があるとも考えられている。
梨(なし)
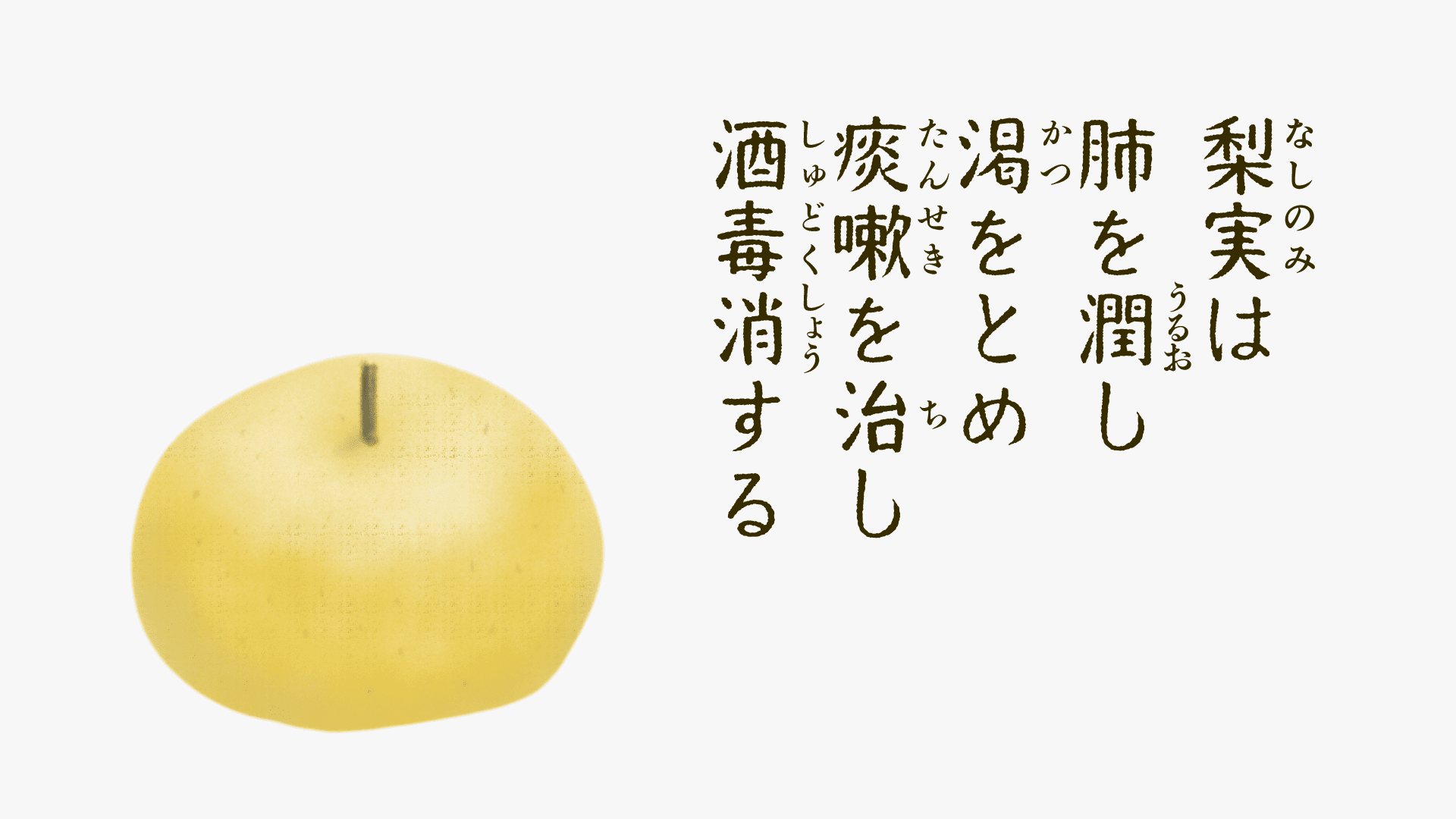
梨は熱性の喉の渇きを伴った咳や痰に効果がある。冷やす性質が強めで、お腹を下しやすい方は食べ過ぎに注意したい。
柿(かき)
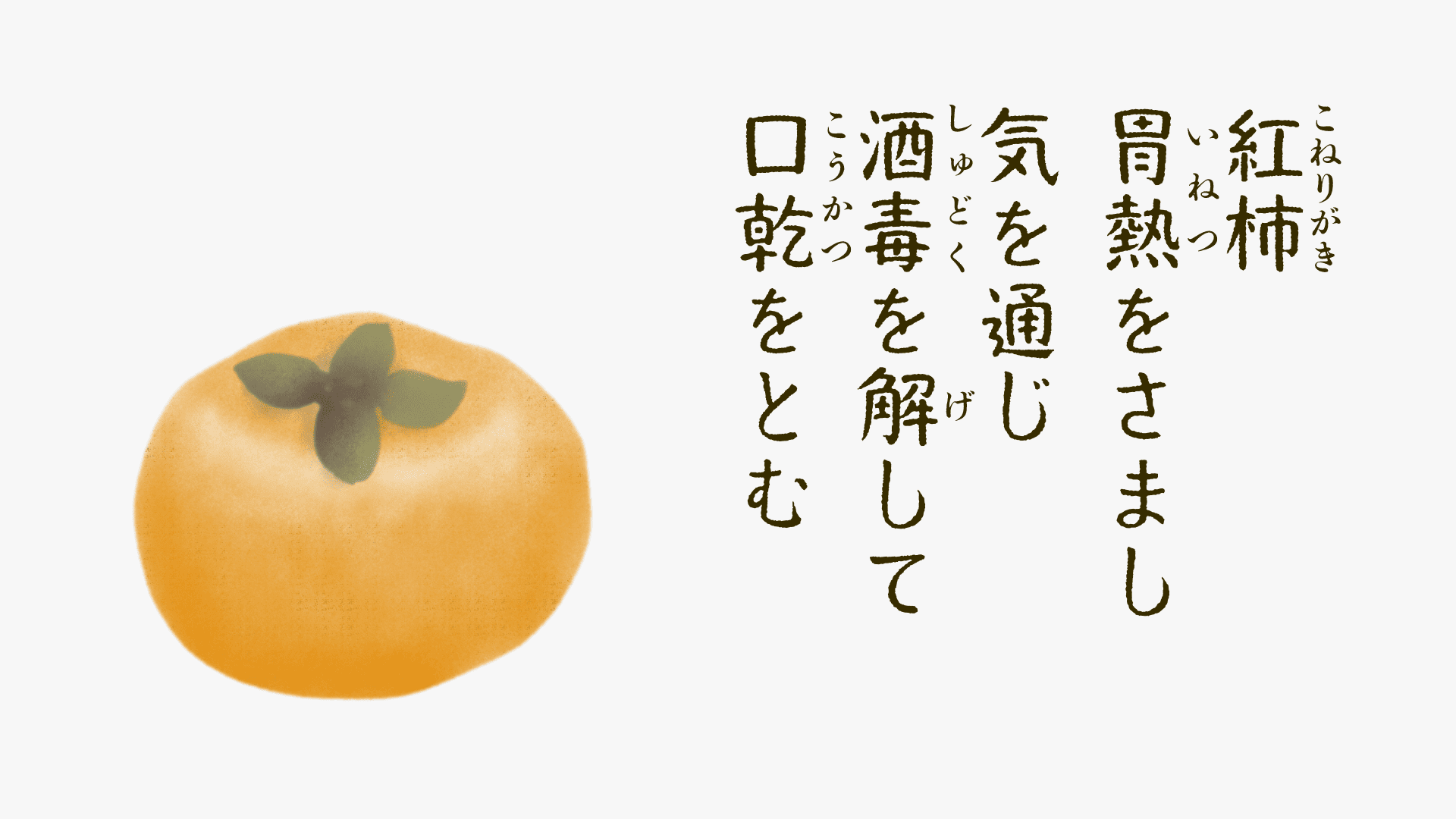
冷やす性質が強く、口の渇きによい。酒の毒を抜くのによく、『本朝食鑑』には飲酒時に干し柿をスライスして臍のせ、帯で固定すると泥酔しないある。
葡萄(ぶどう)
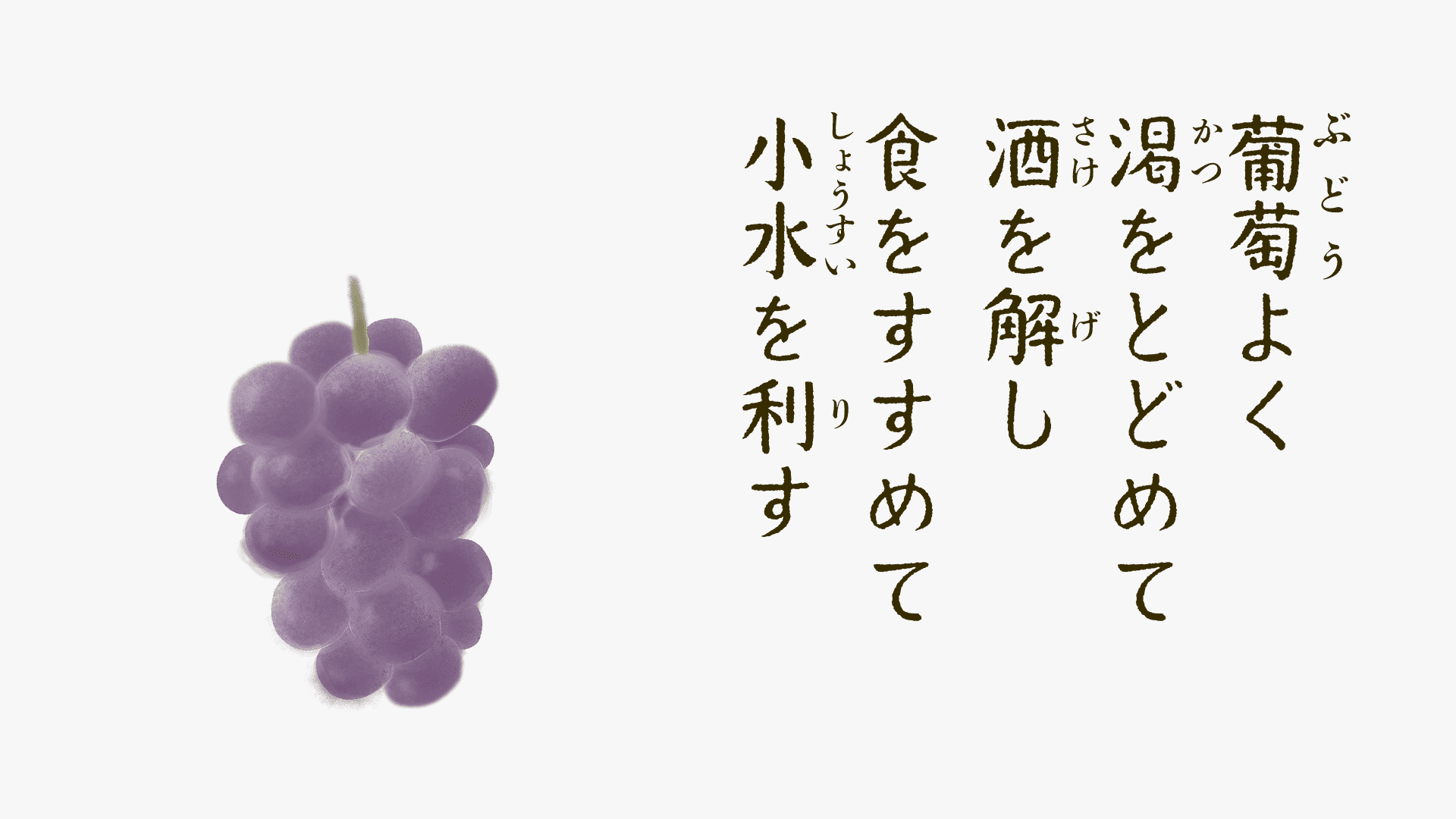
利水作用があり、浮腫み体質の方の筋骨の痛みによいとされる。果物の中では珍しく冷性ではないので、冷え体質の方も量に気をつければ食べられる。できれば常温で食べたい。
鰹(かつお)
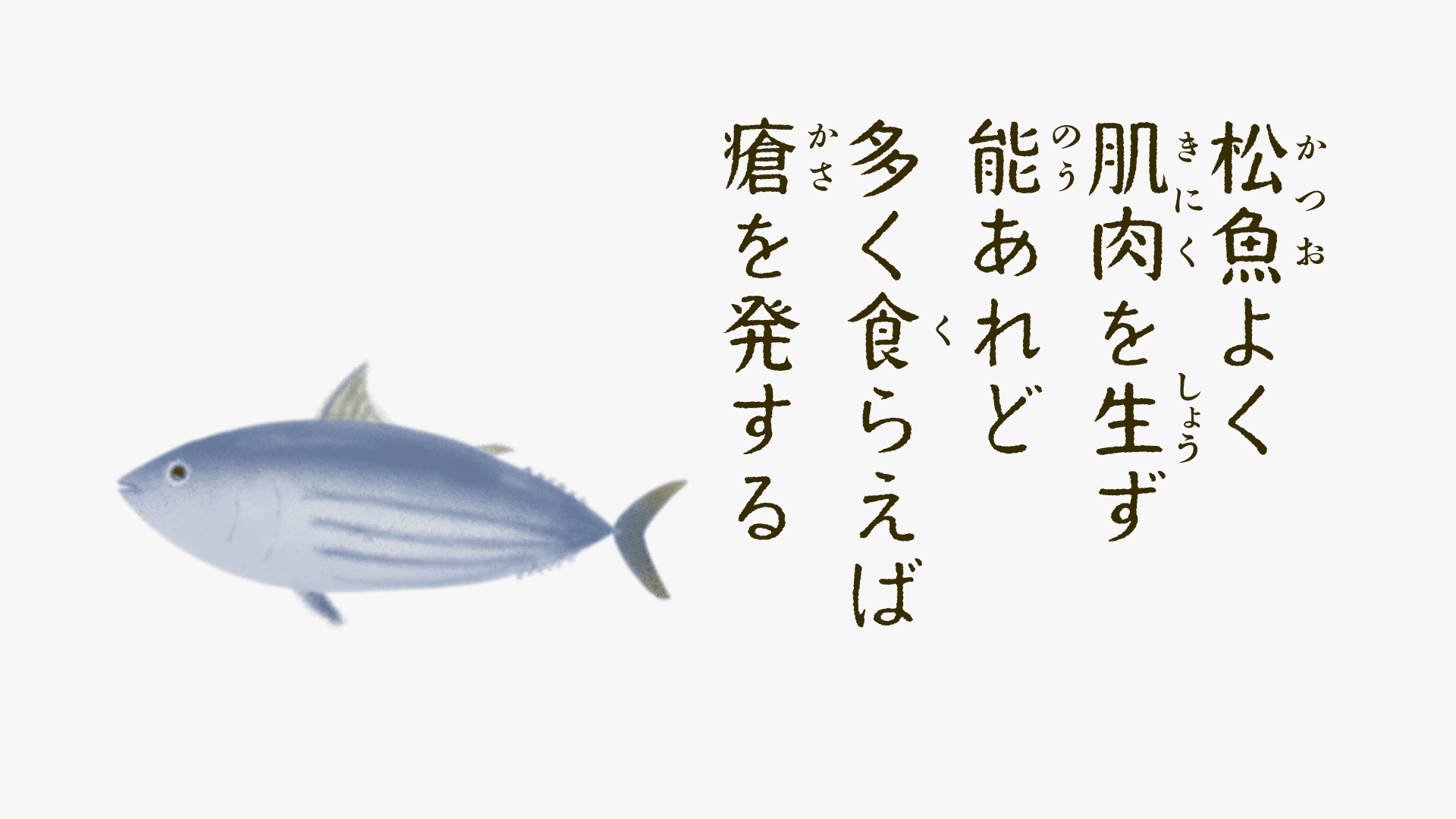
心身の慢性疲労によく、『本朝食鑑』には「凡そ諸病に忌むこと無し、但だ傷寒家これを忌む」とされ、傷寒(感染症)にかかっている時以外は、体質を気にせず食べることのできる食材。補う作用が強いので、食べすぎると皮膚病を生じるともされる。
参考文献
- 大津賀仲安. 食品国歌. 1787年. 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ(シ/204).
- 平野必大. 本朝食鑑. 1697年. 国立公文書館デジタルアーカイブ(184-0108).
- 李時珍. 本草綱目. 中国明代. 国立公文書館デジタルアーカイブ(別042-0008).




